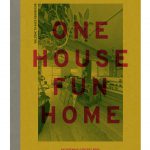築年数で変わるリノベの現実、戸建て・マンションの違いと注意点
物件探しやリノベーションを考えるとき、気になるのが「築年数」について。
築年数はただの数字ではなく、建物の傷み具合やリノベにかかる費用の目安にもなる大事なヒントです。
同じ築年数でも、戸建てとマンションでは事情が違うことも。
木造の戸建てでは柱や基礎の劣化が気になり始め、RC(鉄筋コンクリート)のマンションは構造自体は安定していても、水回りや配管の交換が必要になることもあります。
特に築40年を超える物件では、マンションでは配管更新や戸建てでは外壁の補修まで見直すフルリノベが前提になることも珍しくありません!
築年数を理解しておくと「どこを直す必要があるか」「どれくらい費用がかかるか」がイメージしやすくなります。
戸建て・マンション、それぞれの特徴や構造の違いを押さえつつ、リノベの優先順位を決める参考として築年数をとらえてみましょう。
INDEX
築浅、築古って具体的には築何年?

物件探しやリノベでよく耳にする「築浅(ちくあさ)」や「築古(ちくふる)」という言葉。
なんとなく「新しい」「古い」のイメージはつくけれど実際にはどのくらいの築年数を指すのか、うやむやなイメージを持っていませんか?
実はこの基準は建物の構造や種類によっても変わります。ここでは戸建てとマンションに分けて整理してみましょう。
・築浅=築何年?
まず「築浅」と呼ばれるのは、一般的に築10年未満の物件。
木造戸建てでも基礎や柱の劣化はほとんどなく、屋根や外壁も大きな補修は不要なことが多いです。
マンションであれば鉄筋コンクリート(RC)の構造部分は安定しており、リノベをする場合でも「最新の設備に入れ替えたい」「内装を自分好みに変えたい」といったデザイン変更がメインになることが多数。
工事規模も比較的軽めで済むため、小規模なリノベで完結することが多いです。
また、建物の構造はまだまだ新しいので、築浅物件購入はやはり高額なケースが多く見られます。
物件内見の際は綺麗な状態が魅力的に感じ(特に外観!)、予算オーバーながらも購入を検討するケースがあります。
この場合、リノベ予算が減ってしまう。ということも考えられるので、築浅物件の持つ魅力とやりたいリノベの予算確保に悩む方は多くいらっしゃいます。
このバランス感には気をつけたいポイントです。
・築古=築何年?
一方で「築古」とされる物件は、木造戸建てとマンションで少し数字が異なります。
木造戸建ての場合は築30年以上がひとつの目安です。
木造は湿気やシロアリの影響を受けやすいため、基礎や土台、柱の劣化が進んでいる可能性があります。さらに、耐震補強や断熱改修も考える必要があります。
屋根や外壁の補修、サッシの交換といった大掛かりな工事が必要になるケースも多数。
物件購入費用は抑えられても、リノベで必要な費用は一般的なマンションフルリノベ以上はかかるので、物件購入時にはリノベの費用感も具体的に検討した上で判断されることをおすすめします。
次に、マンションの場合は築40年以上が「築古」とされるのが一般的です。
鉄筋コンクリート造は構造自体は長持ちしますが、給排水管や電気設備などのインフラ部分が寿命を迎える時期です。
特に配管は共用部分に関わることも多いため、リノベを検討する際には管理組合の修繕計画もチェックする必要があります。
築古マンションのリノベは内装デザインの自由度が高い一方、見えない部分の工事に費用がかかる点が特徴です。
ちなみに、築40年以上のマンションのなかには「ヴィンテージマンション」と呼ばれるものもあります。
これは単に古いという意味ではなく、当時の設計や素材、立地条件が今なお高く評価されている物件のことを指します。
重厚感のある外観や、凝った共用部のデザインなど、近頃の築浅マンションでは見られない独自の魅力を持っているのが特徴。
実際に都心部では築年数が古くても人気が高く、資産価値を維持しているケースも少なくありません。
このように築年数が40年を超えたからといって一律に価値が下がるわけではなく、むしろ個性や希少性が評価される例も。マンションの価値は「築年数」という数字だけでは測れないのです。

ちなみに、築10〜20年の物件は「築浅と築古の中間」といった位置づけ。
間取り変更が必要なければ、設備交換や内装リフレッシュだけでも十分です。
築20〜30年の場合、戸建てでは配管・断熱・耐震といった基本性能の改善が必要になってきます。
マンションでも大規模なリノベを予定しているのならば、将来に備えて配管の更新もしておくと安心です。
そして築古ゾーンに入ると、建物全体を見直すフルリノベが前提になるケースも少なくありません。
つまり、「築浅=築10年未満」「築古=木造戸建ては築30年以上、マンションは築40年以上」と覚えておくと、物件探しの際に判断しやすくなります。
ただし同じ築年数でも管理状態やメンテナンス履歴によって劣化度合いは大きく違うため、数字だけでなく現地のチェックも欠かせません。
築年数は単なる数字ではなく、リノベの規模や優先順位、そして予算感を決めるための大切な基準です。
これから物件購入やリノベを検討する方は、ぜひ「築浅」「築古」という言葉を数字とイメージで具体的にとらえてみてください。
自分に合った住まい選びのヒントになりますよ。
代表的な構造「木造・RC・鉄骨」と築年数の関係

建物の寿命やリノベの必要度は築年数だけでなく「構造」によっても異なります。
ここでは、日本の住宅でよく見られる木造・RC(鉄筋コンクリート)・鉄骨造の3つを取り上げ、それぞれの特徴と築年数の関係を整理してみます。
[木造]

△△△木造戸建てのリノベ事例。等間隔で配置した木製の柱・梁で建物を支えます。中央部に見える柱は構造上必要な柱です。
■リノベ事例紹介ページはコチラ▷▷▷自分の時間を楽しく過ごす[Click Here]
日本の戸建て住宅の多くを占めるのが木造です。
木は湿気やシロアリの影響を受けやすいため、築20年を過ぎると基礎や柱、屋根の劣化が目立ち始めます。
築30年以上になると耐震性能が不足するケースもあり、補強工事が必須になることも。
外壁や屋根の塗装、防水処理を定期的にしていれば寿命は延ばせますが、長期間メンテナンスされていない場合は、築浅でも大規模修繕が必要になることがあります。
リノベの際は耐震補強や断熱改修をセットで考えると安心です。
築浅木造戸建てリノベ以外のケースでは、リノベの内容に補修内容も含めておくと良いですね。
[RC(鉄筋コンクリート造)]

△△△RC構造の築52年マンションリノベ。フルリノベをすると見えてくる範囲では築年数の影響は感じにくいですよ。
■リノベ事例紹介ページはコチラ▷▷▷フレキシブルポップ[Click Here]
マンションに多く採用されるRCは、構造的な耐久性が高いのが特徴です。
一般的に耐用年数は47年とされますが、適切なメンテナンスをしていれば60年以上使えることも珍しくありません。
ですので、築古RCマンションを検討の際はメンテナンス履歴を必ず確認しておきましょう。
築20〜30年では配管や設備の更新、築40年以上では給排水管や電気設備の全面的な交換が課題になります。
つまり、構造体自体はしっかりしていても「見えない部分」が劣化しているのがポイント。リノベーションでは、水回りや配管更新をどこまで行うかが費用を左右します。
特に最近増えている「リノベーション済み物件」では、目にみえる部分は非常に綺麗でも、配管や設備の更新はされていないこともあります。
こういった点でも、自身で行うリノベでは何をどこまで手を加えるかが明らか。手間や費用はかかりますが将来的な安心感が違います。
[鉄骨造(S造)]

△△△鉄骨造戸建てのリノベ事例。鉄骨造の特徴は天井のデッキプレートや鉄筋のブレース。こうした部分をあえて見せることで、木造やRC造と違ったデザインに仕上がります。
■リノベ事例紹介ページはコチラ▷▷▷やさしさ時々ラフ[Click Here]
鉄骨造は軽量鉄骨と重量鉄骨に分けられ、戸建てから中低層マンションまで幅広く採用されています。
耐用年数はおおむね34〜40年とされますが、最大の敵は「錆(サビ)」です。
防錆処理がしっかりされていれば長持ちしますが、雨漏りや結露によって鉄骨が錆びると強度が低下することがあります。
築20〜30年の物件では錆や腐食の有無をチェックすることが大切です。リノベ時には、外壁や防水の改修を優先的に考えると安心ですよ。
また、一戸建ての場合、鉄骨造は木造よりも耐用年数が長いことは見逃せないポイント!
一戸建ての築25年でも木造と鉄骨造では、メンテナンス内容が変わってきますので、一戸建ての物件選びの際には「構造」も要チェックです。

このように、同じ「築30年」の物件でも、木造・RC・鉄骨で状況はまったく異なります。木造では構造補強が必要になる一方、RCはまだまだ現役で使えることもありますし、鉄骨は錆の程度によって寿命が左右されます。
つまり、築年数だけで判断するのではなく、構造ごとの特徴と劣化のしやすい部分を理解することが重要です。
構造と築年数をセットで見ることで、物件の「本当の価値」が見えてきます。
築年数より大切?管理状態とメンテナンス履歴

物件選びで「築年数」に注目する人は多いですが、実はそれ以上に大切なのが管理状態やメンテナンス履歴。
なぜなら同じ築30年でも、丁寧に手入れされてきた建物とほとんど放置されてきた建物とでは、実際の劣化具合がまったく違うからです。
たとえば木造戸建て。築30年と聞くと古さを感じるかもしれませんが、定期的に外壁や屋根の塗装を行い、シロアリ対策もしてきた家は、柱や基礎がしっかり保たれていることも多いです。
一方で、築20年程度でも外壁の補修を一度もしていなかった家は、雨漏りや劣化が急速に進み、結果的に大規模な工事が必要になるケースもあります。
築年数よりも「どう手をかけてきたか」で寿命が大きく変わるのです。
マンションも同じです。築40年と聞くと不安に思う人も多いですが、管理組合がしっかり機能し、長期修繕計画に沿って大規模修繕を行ってきたマンションは見た目も内部も意外と健全です。
逆に、築20年でも管理組合が機能しておらず、修繕積立金が不足しているマンションは、給排水管の更新や外壁補修が先送りになり、購入後に思わぬ負担がのしかかることもあります。
チェックのポイントとしては、戸建てなら「外壁・屋根の修繕歴」「シロアリや防水工事の記録」、マンションなら「大規模修繕の実施状況」「修繕積立金の残高や今後の計画」が重要です。
これらは内覧や資料請求の段階で確認できることが多く、不動産会社や売主に遠慮なく質問してOKです。
つまり、築年数はあくまで目安にすぎません。築30年だからダメ、築10年だから安心という単純な線引きはできず「どのように管理され、どんなメンテナンスを積み重ねてきたか」が住まいの健康寿命を左右します。
リノベーションを前提に物件を探すなら築年数にとらわれすぎず、管理状態やメンテナンス履歴をしっかり見極めることが大切です。
それが「良い物件との出会い」のコツですよ。
時々見かける壁式構造マンションと築年数の関係

壁式構造とはマンションなどに使われる構造の一つで、柱や梁を使わずに鉄筋コンクリートの壁そのものが建物を支える仕組みです。

△△△こちらのリノベ事例は、テレビ背面の壁が壁式構造の躯体壁。構造なので壊せませんが、リノベ事例のようにコンクリート面をあえて見せるデザインが可能です。
■リノベ事例紹介ページはコチラ▷▷▷綯交(ないまぜ)な暮らし[Click Here]
壁式構造は、主に5階建て以下の中低層マンションに採用される構造で、鉄筋コンクリートの壁全体で地震の揺れを受け止めるため、耐震性に優れているといわれます。しかし、この強みも「築年数」によって評価が変わります。
まず大きな分かれ目は、1981年の新耐震基準です。これ以降に建てられた壁式構造マンションは、震度6強〜7程度の地震でも倒壊しないことを前提に設計されており、耐震性能は高いと考えられます。
一方、1981年以前の「旧耐震基準」で建てられた物件では、壁の配置や厚さが現行基準を満たしていない場合があり、耐震診断や補強が必要になるケースもあります。築40年以上の壁式マンションを検討する際は、まずこの点を確認することが欠かせません。
また、築年数が経つとコンクリートの劣化や鉄筋の腐食が進むことがあります。
壁式構造は柱や梁ではなく壁全体で建物を支えているため、ひび割れや劣化が進行すると、耐力壁の性能に直結します。
築30年以上の物件では、外壁や防水工事の履歴、鉄筋の状態を確認することが特に重要です。
さらに、築年数が古い壁式マンションでは、リノベーションの自由度にも影響が出ます。
耐震性を保つために壁の撤去や大きな開口を設けることができず、「間取りを大幅に変える」ことが難しいため、築古物件を購入して理想の間取りにリノベしたい人には制約が大きいと感じられるかもしれません。
つまり、壁式構造は新耐震基準以降の築年数であれば耐震性において非常に安心感のある構造ですが、築40年を超えるような物件では、劣化状況のチェックと旧耐震のリスク確認が必須です。
築年数との関係をしっかり押さえることで、安心して選べる壁式マンションに出会えますよ。
気になる築年数と資産価値の関係

物件を選ぶとき、築年数やリノベのしやすさに加えて気になるのが「資産価値」。
特に将来的に売却や賃貸に出す可能性がある場合、築年数と資産価値の関係を理解しておくことはとても大切です。
一般的に、築年数が浅い物件ほど資産価値は高く、年数が経つごとに下がります。
ただし、これは建物部分の価値に限った話。
土地付きの戸建ての場合は「土地の価値」が大きな割合を占めるため、築年数が経っても一定の資産性を維持できることがあります。
一方、マンションは土地の持分が小さいため、建物自体の価値と管理状態が資産価値に直結しやすいのが特徴です。
築20年程度までは資産価値の下落が大きく、その後は緩やかになる傾向があります。
築30〜40年を超えると「古いから価値がない」というよりも、「適切に管理されてきたかどうか」で大きな差が出ます。
修繕積立金がしっかり機能しているマンションや、耐震補強・外壁修繕が行き届いている戸建ては、同じ築年数でも資産価値を維持しやすいです。
また近年は、築古でもフルリノベ済みの物件が市場で一定の人気があります。
「古いけれど中身は新しい」状態にすることで、購入希望者にとって安心材料となり資産価値が下支えされるケースもあります。
ちなみにこの場合、いくら中身は新しくても個性が強すぎるデザインや間取りの場合には、資産価値に繋がらないことも見られます。
資産価値を重視するのであれば、内装デザインよりも、見えない部分のメンテナンスを充実すると好印象に繋がります。
逆に、管理が不十分で劣化が進んでいる物件は、築浅でも評価が落ちやすいので注意が必要です。
つまり、資産価値は単に築年数の長さだけで決まるものではなく、土地の条件・構造の種類・メンテナンスの履歴といった要素が組み合わさって形成されるもの。
築年数はあくまで目安であり、「どう管理され、どう住み継がれてきたか」が将来の資産性に直結します。
リノベを考える際も、将来の資産価値を見据えて、築年数と管理状態をセットでチェックすることが大切です。

築年数は物件選びやリノベの大切な目安ですが、数字だけで判断するのはもったいないポイント。
同じ築30年、築40年の物件でも、構造や管理状態、過去のメンテナンス履歴によって劣化の程度やリノベのしやすさは大きく変わります。
木造戸建ては柱や基礎の状態を、RCや鉄骨造は配管や鉄筋の劣化をチェックすることが重要です。
さらに、資産価値の面でも築年数は一つの目安に過ぎません。
土地の価値や管理状況、フルリノベーションの有無によって、同じ築年数でも評価は大きく異なります。
築古物件でも丁寧に手入れされ、必要な補修が行われていれば安心して暮らせる住まいになります。
リノベを考えるなら、築年数を「ネガティブ要素」と思うのではなく、物件を知るための情報としてポジティブに捉えることが大切。
構造や管理状態、資産価値を総合的に見極めることで、満足度の高い住まいに出会えるはずです。
築年数を理解しながら、安心で快適なリノベ計画を進めましょう。
_________________________________________
▼▼施工事例▼▼
ハコリノベの事例一覧はこちら >> 施工事例
▼▼EVENT▼▼
見学会情報や相談会はこちら
>> 関西エリアイベント情報
>> 関東エリアイベント情報
_________________________________________
(ご来店希望日時をコメントにご記入願います!)